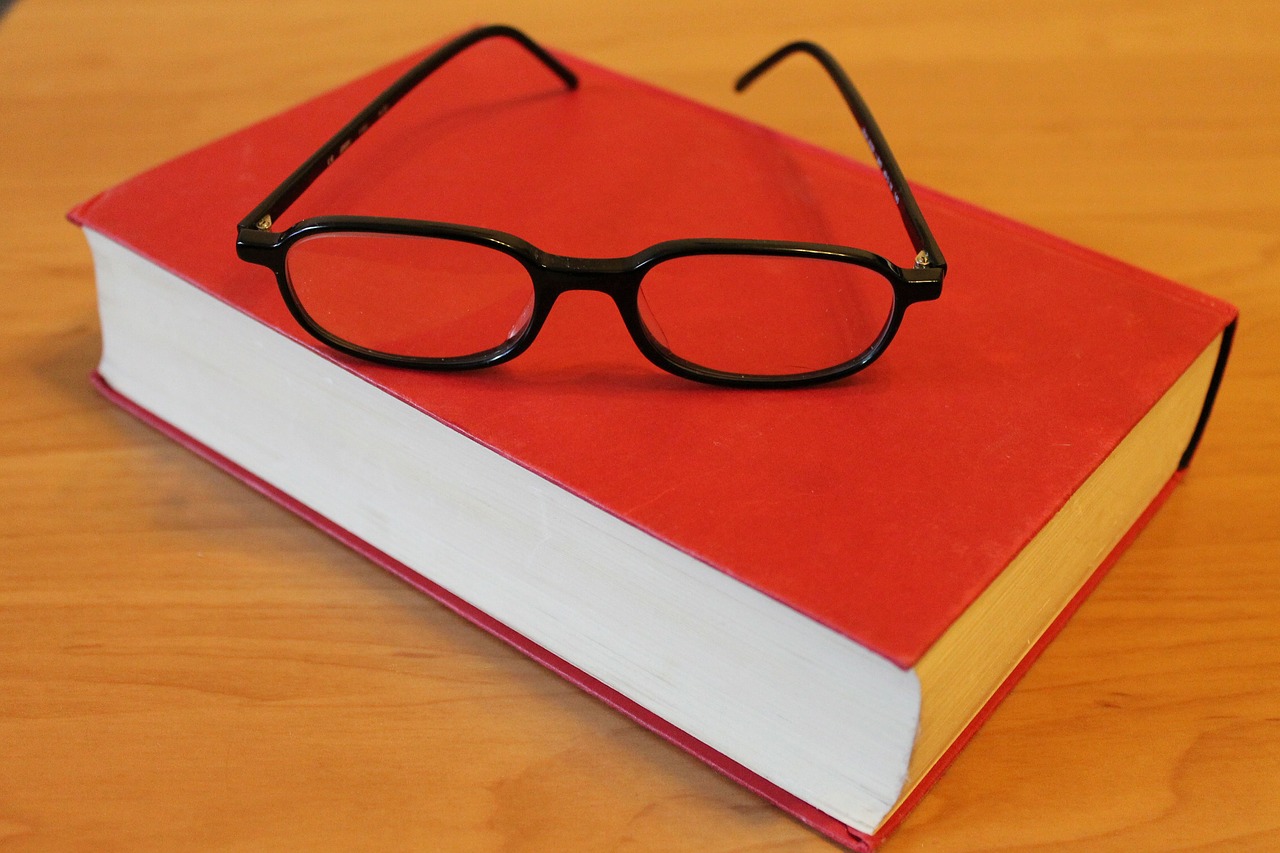アフラック夢みるこどもの学資保険の口コミ・評判は?FPが返戻率や特徴を評価2025最新版
目次
夢みるこどもの学資保険~特長・メリット・デメリットと賢い活用法~
子どもの高校・大学進学には、多額の教育資金が必要です。日本政策金融公庫の調査によれば、高校入学から大学卒業までにかかる教育費は平均で942.5万円にも上ります。
こうした将来の教育費を計画的に準備できる貯蓄型の保険商品として、多くの家庭で選ばれているのがアフラック「夢みるこどもの学資保険」です。
この記事では、中立的な立場からこの商品の特徴やメリット・デメリットを詳しく解説し、他の学資保険や貯蓄方法とも比較しながら、賢く教育資金を準備するポイントをご紹介します。
学資保険とは?教育資金を準備する保険の基本
まず、「夢みるこどもの学資保険」の内容に入る前に、学資保険とはどのような保険なのか基本を押さえておきましょう。
学資保険とは、子どもの教育費を計画的に積み立てるための貯蓄型の生命保険です。
契約者(通常は親)が一定期間保険料を支払い、子どもが高校入学や大学進学を迎えるタイミングに合わせて祝い金や満期保険金(学資金)を受け取る仕組みになっています。
一般的には子どもが0歳~6歳頃までに契約し、15年から22年程度かけて保険料を払い込むケースが多くみられます。
学資保険のメリットは、大きく以下のような点にあります。
貯蓄性が高いこと:銀行預金より利率が良い場合が多く、支払った保険料総額より多い額の学資金を受け取れる可能性があります(後述する返戻率で確認できます)。
契約者に万一のことがあっても保障されること:契約者である親に万が一のこと(死亡・高度障害など)があった場合、以後の保険料支払いが免除され、満期時には予定通りの学資金が受け取れる「保険料払込免除」の保障が付いている商品が一般的です。
親に万が一のことがあっても子どもの教育資金が確保される安心感があります。
強制的な積立効果:契約すると決まった保険料を払い込む義務が生じるため、計画的かつ確実に教育資金を積み立てられます。
つい使い込んでしまう心配がなく、確実に貯蓄できる点は大きな利点です。
一方、デメリットや注意点もあります。
途中解約のリスク:満期前に解約すると「解約返戻金」は払い込んだ保険料総額より少なくなり(元本割れ)、大きな損失が発生する可能性があります。
学資保険は長期契約なので、一度加入したら満期まで続けることが前提です。
インフレに弱い:契約時に定めた受取額は満期まで固定されます。
物価や学費が将来上昇した場合、受け取った学資金の実質的な価値が目減りする可能性があります。
資金の流動性が低い:学資保険は基本的に満期や約定の支給時期までお金を引き出せません。
急な出費で資金が必要になっても、途中で取り崩すと元本割れのリスクが高いため、流動性は預金などに比べて低いです。
以上が学資保険全般の基本的な特徴です。それでは、アフラックの「夢みるこどもの学資保険」について、具体的な内容を見ていきましょう。
アフラック「夢みるこどもの学資保険」の特徴
「夢みるこどもの学資保険」は、アメリカンファミリー生命(アフラック)が提供する学資保険で、高校入学時と大学在学中の4年間という教育費のかかる時期に合わせて給付金を受け取れるプラン設計が最大の特徴です。
以下、この商品の主な特徴を整理します。
教育資金を進学時期に集中して受け取れる: 高校入学時に学資一時金(祝い金)を、大学入学時から4年連続で学資年金(学資保険金)を受け取ることができます。
例えば大学入学時にまとまった資金を受け取り、その後毎年学費相当額を受け取れるため、一度に多額の出費が重なるのを防ぎ計画的に資金を充当できます。
実際、ユーザーからも「高校入学時と大学入学時という一番お金がかかる時期に給付金を受け取れる点が魅力的」という口コミが寄せられています。
契約可能年齢と加入タイミングの柔軟性: 子どもが0歳から契約可能で、出生予定日の140日前(妊娠6か月頃)から申し込みできます。
出産前に契約しておけば、生まれてから慌ただしくなる時期を避け、落ち着いて教育資金プランを準備できます。
子どもが加入できる年齢上限は、基本プラン(後述の17歳払済・18歳払済)なら満7歳の誕生日の前日まで、短期払込プラン(10歳払済)なら満5歳の誕生日の前日までとなっており、比較的加入可能な期間が長めです。
学資年金受取開始年齢を選択可能: 学資年金(大学在学中の年金)の受取開始年齢は17歳か18歳から選べます。
17歳を選ぶと高校卒業前に最初の年金を受け取れるため、大学入学前の出費(入学金納付など)に充てやすくなります。
18歳開始を選ぶと最初の年金受取が大学入学後になる場合がありますが、その分契約期間が長く返戻率が若干良くなる傾向があります(契約日によっては大学入学手続きより支払いが後になる可能性があるため要確認)。
家庭の予定に合わせて選択できる柔軟性は嬉しいポイントです。
受取総額(コース)を柔軟に設定可能: 受取総額(学資一時金+学資年金4回の合計額)は120万円から1,500万円まで、60万円単位で自由に設定できます。
たとえば「受取総額300万円コース」や「受取総額600万円コース」といった具合に、各家庭の予算や目標に合わせてコースを選べます。
幅広い金額帯に対応しているので、「私立大学に備えて手厚く準備したい」「最低限の学費だけ準備したい」といったニーズに応じて金額を調整できるのも特徴です。
保険料払込期間を選べる: 保険料の払い込み期間(払込期間)は3つのプランから選択可能です。
標準的なプランは子どもが17歳になるまで払い込む「17歳払済」または18歳までの「18歳払済」で、大学入学直前までコツコツ積立てるイメージです。
さらに、教育費の本格的な負担が始まる前に払い込みを終えてしまいたい方向けに、子どもが10歳になるまでに一括で払い込む「10歳払済」プランも選べます。
例えば住宅購入など他の大きな支出イベントが控えている場合、子どもが中学校に上がる頃(10歳)までに学資保険の払い込みを完了させておけば、その後の家計管理が楽になるメリットがあります。
保険料払込免除特則(契約者の保障): 学資保険の大きな安心材料として、契約者(親)が万一死亡または高度障害状態になった場合に、その後の保険料払い込みが免除される「保険料払込免除特則」を付加できます。
この特則を付けておけば、万一の場合でも以降の保険料負担なしで契約を継続でき、子どもは予定通り学資金を受け取れます。
アフラックの学資保険ではこの保障が基本契約に自動付帯(特則扱い)となっており、別途オプション料金なしで万一の備えがされています。
一家の主要な収入源である親に万一があっても教育資金が確保されるのは、大きな安心と言えるでしょう。
医師の診査が不要で手続き簡単: アフラックの学資保険は健康状態にかかわらず医師の診断書や診査が不要で申し込めます。
持病や妊娠中でも加入しやすく、手続きが簡便です。
実際の利用者からも「医師の診断が不要で手間がなく良い」という声があり、スムーズに加入できたとの口コミも見られます。
保険料支払い方法も選択可(クレジットカード払い対応): 保険料の支払いは月払い・半年払い・年払いに加え、全期分を契約時に一括前納することも可能です。
特にクレジットカード払いに対応している点は珍しく、アフラック学資保険のメリットと言えます。
月払い・年払い問わずカード決済が可能なので、クレジットカードのポイントを貯めつつ支払うこともできます。
学資保険は総支払額も大きく長期にわたるため、カードポイントの恩恵は馬鹿にできません。
ただしカード払い対応かどうかは販売窓口による場合もあるため、契約時に確認すると良いでしょう。
以上が「夢みるこどもの学資保険」の主な特徴です。まとめると、「0歳から契約でき、教育費のかかる高校・大学時に合わせて給付金を受け取れる」、「受取総額や払込期間を柔軟に選べる」、「契約者に万一のことがあっても保障される」といった点がポイントです。
では、次に気になる返戻率や保険料シミュレーションについて見ていきましょう。
返戻率と保険料シミュレーション:どれくらい得になる?
返戻率(へんれいりつ)とは、支払った保険料総額に対して受け取れる総額がどれくらいの割合になるかを示す指標です。
返戻率=(受取総額÷支払保険料総額)×100(%)で計算され、100%を上回れば「支払総額より多く受け取れる」こと、下回れば「支払総額より少なくなる(元本割れ)」ことを意味します。
学資保険選びでは一つの目安となる数字です。
アフラック「夢みるこどもの学資保険」の返戻率は、契約条件によって幅がありますが、おおむね105%前後と考えておくと良いでしょう。
例えば、もっとも一般的なケースである18歳払済(子ども18歳まで保険料払い込み)・月払いの場合、返戻率は約104~105%程度となります。
一方で、保険料の払い込み方を工夫することで返戻率をさらに高めることも可能です。
支払い方法を年払いや契約時の一括前納にすると、保険会社に早期に資金を預ける分、利回りが向上し返戻率は106~113%前後まで上昇します。
特に10歳払済の短期払いプランを選び、かつ年払いで前倒し拠出する組み合わせにすると、2025年現在の試算では返戻率約112.9%といった高い数値も実現可能です。
ただし注意したいのは、契約内容や払い込み条件によっては返戻率が100%を下回る可能性もある点です。
アフラック公式サイトでも「契約時の年齢や保険料払込期間などによっては、受取総額が払込保険料の累計を下回る場合があります」と明記されています。
特に月払いで短期払込(例えば10歳払済)を選択すると、低金利環境下では保険会社が運用益を出しづらいため、払い込む保険料総額が受取額より多くなってしまうケースもあります。
実際、過去のデータでは2017年の利率改定後、この商品の返戻率は最大でも98%程度(元本割れ)との試算もありました。
現在では払い込み方法次第で100%を超えることも可能ですが、「必ず得をする」とは限らないことは認識しておきましょう。
モデルケースで見る保険料と返戻率
では、具体的にどのくらいの保険料を支払い、いくら受け取れるのか、いくつかモデルケースを示してみます(契約者は30歳男性、子ども0歳の場合の目安)。
自分の家庭の予算感と照らし合わせる参考にしてください。
ケース1:受取総額300万円コース、18歳払済(月払い)
最も基本的なプラン設定の一例です。子どもが18歳になるまで毎月保険料を支払い、高校入学時50万円+大学1年時100万円+大学2~4年時各50万円で合計300万円を受け取る契約です。
この場合、月々の保険料は約1万3,000円前後となり、18年間の払込総額は約285~286万円です。
受取総額300万円に対して払込総額が約285万円となるため、返戻率は約105%(支払った額の105%を受け取れる)になります。
例えば世帯年収500万円程度のご家庭であれば、月々1.3万円の保険料負担は家計の数%に収まり、無理のない範囲で計画的に教育資金を準備できるモデルケースと言えるでしょう。
ケース2:受取総額300万円コース、10歳払済(年払い)
教育費の本格化する前に払い込みを完了し、かつ返戻率を高めたい方向けのプラン例です。
子ども10歳までの10年間で保険料を払い終え、高校入学時50万円+大学4年間計250万円を受け取る契約とします。
この場合、保険料は年払いで毎年約26万5,000円の支払いとなり(10年間合計約265万円)、月額換算では約2万2,000円のイメージです。
払込総額265万円に対し受取総額300万円となるため、返戻率は約112.9%と非常に高くなります。
毎月の負担額はケース1に比べて大きくなりますが、教育費を先に払い終えてしまえる安心感と高い貯蓄性が得られるプランです。
例えば世帯年収800~1000万円程度で早いうちに教育資金のメドをつけたい家庭や、祖父母から早期に教育資金の生前贈与を受けている場合などに適したケースでしょう。
ケース3:受取総額180万円コース、18歳払済(月払い)
家計負担を抑えて最低限の教育資金だけ準備したい方向けのプラン例です。
高校入学時30万円+大学4年間計150万円を受け取るコース(合計180万円)で、子ども18歳まで月払いする場合、月々保険料はおよそ8千円前後と見込まれます(契約者年齢等により異なります)。
18年間の払込総額は約170~180万円程度となり、受取総額180万円とほぼ同程度かやや上回る水準です。
返戻率にするとおよそ100~102%程度で、貯蓄性は高くありませんが確実に必要資金を積み立てられる安心感があります。
家計に大きな余裕はないが児童手当などを活用しつつ手頃な保険料で教育費を準備したい、といったご家庭に向いたケースです。
※上記モデルケースはあくまで概算の一例です。実際の保険料は契約者の年齢や性別、加入時期や払込方法、特約の有無などによって異なりますので、詳しくはアフラック公式サイトのシミュレーション機能や担当者への確認をお勧めします。
以上のシミュレーションから分かるように、「夢みるこどもの学資保険」は払い込み方次第でおトク度(返戻率)が変わる商品です。
家計に無理のない範囲で払込期間や方法を選び、可能であれば年払い等を活用することで、より有利に教育資金を準備できるでしょう。
アフラック学資保険のメリット
では、改めてアフラック「夢みるこどもの学資保険」のメリットを整理してみます。
他社商品や他の資金準備方法と比べた際に、どのような利点があるのか確認しましょう。
主なメリット(長所):
教育費が必要な時期に確実に資金を用意できること
高校入学時や大学入学時といった教育費のピークに合わせて給付金を受け取れる設計のため、計画的に資金準備ができます。
特に大学入学時にはまとまった入学金や初年度授業料の支払いが発生し、その後も在学中毎年学費がかかります。
アフラックの学資保険なら高校入学時の一時金で高校進学費用をカバーし、大学4年間の年金で授業料や生活費に充てるなど、段階的に家計負担を軽減できます。
必要な時に必要な額を受け取れる安心感は大きなメリットです。
万一の際の保障(保険料払込免除)があること
契約者(親)が死亡・高度障害状態・不慮の事故による重度障害状態になった場合、以後の保険料払込みが免除され、子どもは契約どおり学資金を受け取れます。
この「保険料払込免除特則」により、家庭の主要収入者に万一があって収入が絶たれた場合でも、子どもの教育資金だけは確保されます。
生命保険としての保障機能が付いている点は、単に貯蓄する場合にはないメリットです。
「もしもの時にも子どもの学費を残せる」という安心感は、子育て世帯にとって大きな価値と言えるでしょう。
大手保険会社ならではの信頼感と安心感
アフラックは日本では1974年から営業を開始し、がん保険をはじめ長年実績を積んできた大手保険会社です。
累計契約件数も数千万件規模に上り、保険金支払いの確実さや顧客対応にも定評があります。
学資保険は長期契約になりますから、保険会社の安定性や信頼性は重要なポイントです。
経営基盤のしっかりしたアフラックの商品であること、さらに営業職員や代理店のサポート体制が整っていることは利用者にとって安心材料でしょう。
実際、口コミでも「資料請求や問い合わせに迅速・丁寧に対応してくれた」「担当者の対応が良かった」等、顧客対応面で高評価の声が見られます。
払い込み方法の選択肢が多く計画に合わせやすい
前述のとおり、保険料の払込期間を3通りから選べるため、家庭の計画に合わせやすいです。
例えば「住宅ローン返済が落ち着く10年後までに学資保険も払い終えておきたい」「子どもが高校・大学に進む頃は他の出費もかさむから、その前に払い込み終了させたい」といった要望に応えられます。
また支払い方法も月払い・年払い・一括前納から選べるので、ボーナス時にまとめ払いして利率を上げる等の工夫も可能です。
柔軟な設計で家計管理上のメリットが大きいと言えます。
貯蓄性と利便性のバランスが良い
学資保険全般に言えることですが、銀行預金でコツコツ貯めるより利回りが良くなる可能性が高いのは魅力です。
現在のような低金利時代では普通預金や定期預金の利息はごくわずかですが、学資保険なら契約時に決まった利率で計画的に増やせる期待があります(※利率は保険会社の運用環境により変動するため一概には言えません)。
また、アフラックの学資保険は契約者貸付制度(積立金の範囲内で保険会社から貸付を受けられる制度)も利用できます。
万一途中で資金が必要になった際は解約せずに貸付を活用でき、柔軟性も一定程度確保されています。
強制貯蓄しながら、困った時には貸付で乗り切ることもできる点で利便性とのバランスも取れています。
以上のように、「夢みるこどもの学資保険」は教育資金準備の手段として多くのメリットを備えています。
計画的な資金準備・万一への備え・貯蓄性という学資保険に求められる機能をバランス良く満たした実力派の商品と言えるでしょう。
アフラック学資保険のデメリット・注意点
一方で、この商品ならではのデメリットや注意すべきポイントもあります。
他の金融商品や学資保険と比較した場合の課題を理解しておきましょう。
主なデメリット(短所):
返戻率の水準が突出して高いわけではないこと
現在の低金利環境下では、アフラックの学資保険の返戻率はだいたい105~113%程度に留まっています。
確かに銀行預金より有利ではありますが、学資保険の中には返戻率120%以上を謳う商品も存在します。
例えばソニー生命やフコク生命の学資保険などは、高い貯蓄性で人気を集めています(その分、契約条件が厳しかったり加入手続きに手間がかかったりする場合もありますが)。
返戻率の数字だけを見ると業界トップではないため、「とにかく増やしたい」という方には物足りなく感じられる可能性があります。
ただし学資保険選びで大切なのは返戻率だけではありません。他社と比較する際も、保険会社の財務健全性や保障内容の柔軟性、サービス面など総合的に判断することが重要です。
インフレ・物価上昇による目減りリスク
将来もしインフレで物価や学費が上がった場合、契約時に設定した給付金額では不足する可能性があります。
例えば受取総額300万円で契約しても、20年後に学費が大幅に上昇していれば300万円では足りなくなるかもしれません。
現在日本銀行は物価目標を年2%としていますが、仮に毎年2%ずつ物価が上がれば、20年後には当初の300万円の価値は実質的に約200万円台後半に目減りする計算になります。
契約時には十分だと思えた額でも将来不足するリスクがある点は認識しておきましょう。
学資保険だけでなく預金など元本確保型の資金準備策全般に言える課題ですが、インフレ局面では相対的に不利になります。
途中解約に弱い(流動性の低さ)
先述のように、学資保険は長期契約ゆえ途中解約時のペナルティが大きいです。
契約後まもない時期に解約すると解約返戻金が支払額を大きく下回り、元本割れどころか払込済み保険料の大半が戻ってこないこともあります。
契約から一定期間は解約返戻金がゼロという商品もあります。アフラックの学資保険でも、満期前に解約すれば元本割れとなるのは避けられません。
「とりあえず入ってみて、必要なくなったら解約すればいい」という考えは通用しないので注意しましょう。
契約時には満期まで支払い続けられる金額かどうか慎重に見極める必要があります。
契約内容の柔軟性に制約がある
学資保険全般に言えますが、一度契約すると後からプラン変更ができない点にも注意が必要です。
例えば途中で「もっと保険金額を増やしたい」「払込期間を延ばしたい」と思っても、原則として契約後に内容を変更することはできません。
追加で別契約を結ぶか、貯蓄等で補うしかないのが実情です。またアフラックの商品は受取時期のパターンが高校+大学4年のみで固定されています。
他社には中学入学時や大学卒業時に祝い金が出るプランなどもありますが、アフラックの場合は契約コースによる受取総額の違い以外に受取タイミングのバリエーションはありません。
ご自身の教育プランによっては、他社の商品設計の方が合う場合もあるでしょう。
付帯できる保障が限定的
「夢みるこどもの学資保険」には、基本的に子ども向けの医療特約や特定疾病保障などは付加できません。
あくまで教育資金準備に特化した商品であり、例えば子どもの入院保障などは別の医療保険で備える必要があります。
一部の保険会社では学資保険に医療特約を付けられる商品もありますが、アフラックは学資保険と医療保険を別商品として用意しています(アフラックには0歳から入れる「ちゃんと応える医療保険」などがあります)。
そのため、子どもの医療保障もまとめて準備したい方にとっては物足りないかもしれません。
ただし特約がない分、シンプルで分かりやすく、貯蓄に特化しているとも言えます。
以上が主なデメリット・注意点です。まとめると、「夢みるこどもの学資保険」は貯蓄性はあるもののトップクラスではないこと、途中解約やインフレに弱いこと、保障や設計の柔軟性に限りがあることに留意が必要です。
ただし、これらは程度の差こそあれ学資保険全般に共通する課題でもあります。
学資保険はあくまで教育資金準備の一手段として位置づけ、他の資金運用方法(預金、学資用の投資信託、児童手当の活用等)とも比較検討した上で、自分たち家族に合った方法を選ぶことが大切です。
「夢みるこどもの学資保険」が向いている人・向いていない人
以上の特徴・メリット・デメリットを踏まえると、アフラックの学資保険がどういったご家庭にフィットするのかが見えてきます。
ここではこの商品に向いている人の特徴と、反対に向いていない人の特徴を整理してみます。
向いている人:
子どもの高校・大学進学に備えて、計画的かつ確実に教育資金を積み立てたい人。
貯蓄が苦手でも強制的に積立でき、必要な時期に確実に給付金を受け取れるので、「気づいたらお金が貯まっていなかった」という事態を避けたい人に適しています。
万一の保障も重視したい人。
学資保険には親に万一のことがあっても学費を残せる保障が付いているため、自分に万が一のことがあっても子供の学費だけは残したい、と考える方に向いています。
大手保険会社の信頼感を重視する人。
長期間の契約になるため、知名度・信頼度の高い会社に任せたい方にアフラックのブランドは安心材料となるでしょう。
「多少利回りが他より低くても、有名な会社で安心して預けたい」という方にはフィットします。
教育資金づくりと他のライフプランのバランスを重視する人。
払込期間を選べるため、住宅ローンや他の支出との兼ね合いで「◯歳までに払い終えたい」といった計画がある方に向いています。
例えば「子どもが中学に上がる前(10歳)までに学資保険を終わらせ、その後の収入は高校・大学の生活費に充てたい」など、家計全体を見通して設計したい人にとって使い勝手の良い商品です。
クレジットカード払いでポイントを貯めたい人。
学資保険の中でも珍しくカード払込みができるので、日頃からポイントを活用して家計の助けにしたい方にはメリットがあります。
向いていない人:
教育資金の準備に対し、より高い運用リターンを求める人。
少しでも多く増やしたい、高い利回りを重視したいという方には、返戻率105~110%程度の学資保険では物足りないかもしれません。
投資信託や株式などリスク商品での運用を検討できる方や、自分で積極的に資産運用する意思がある方にとっては、学資保険の利回りは低く感じられるでしょう。
資金の流動性を重視する人。
将来何があるか分からないので手元資金はなるべく流動的に持っておきたい、と考える方には不向きです。
学資保険は基本的に満期まで引き出せず、途中で解約すれば損失が発生します。
急な出費やライフプランの変化に柔軟に対応したい人は、学資保険よりも普通預金や流動性の高い金融商品で貯めておく方が安心でしょう。
長期の保険契約に縛られたくない人。
「毎月決まった保険料を何十年も払い続けるのは負担」「将来状況が変わるかもしれないのに契約を固定したくない」という方には向きません。
学資保険は契約後にプラン変更ができないため、ライフステージの変化に柔軟対応するには不利です。
将来の不確実性を考慮して、もう少し自由度の高い貯蓄方法を好む人には合わないでしょう。
子どもの進路が不確定な人。
例えば「大学には行かずに専門学校や就職の可能性もある」「留学や大学院進学などで必要時期がずれるかもしれない」といった場合、給付タイミングが固定された学資保険はミスマッチとなる可能性があります。
教育費として使わなくても給付金は受け取れますが、本来の目的がなくなると利回りの低い金融商品になってしまいます。
そのため、子どもの進路が多様に変わり得ると考える方にも、他の貯蓄手段(必要に応じて使える預金や学資用の投資信託等)の方が向いているかもしれません。
以上を参考に、自分たち家族の考え方や状況に合っているかどうか判断してみてください。
学資保険は万人にとって絶対必要なものではありませんが、ハマる家庭にとっては心強い味方となります。
逆に合わない家庭にとっては非効率にもなり得るので、向き不向きを見極めることが大切です。
加入方法と受け取りまでの流れ
最後に、アフラック「夢みるこどもの学資保険」に実際に加入する方法や、契約後の給付金の受け取り手続きについて簡単に触れておきます。
加入の方法:
資料請求・相談: アフラックの公式サイトや代理店経由で資料請求が可能です。
公式サイトの情報請求フォームから申し込むと、担当の募集代理店から連絡があります。
学資保険は保障内容の確認のため対面での説明・手続きが必要(オンライン完結不可)となっているので、資料請求後は電話や対面でプラン内容の確認を行い、正式申し込みという流れになります。
保険ショップやファイナンシャルプランナー経由で相談・契約することもできます。
申込に必要なもの: 契約者(親)と被保険者(子ども)の個人情報、子どもの生年月日(出生前の場合は出産予定日)などが必要です。
健康状態の告知は不要ですが、妊娠中の申込みの場合は妊娠何ヶ月か等の申告が必要になることがあります。
また、保険料払込免除特則を付加する場合、契約者の年齢が所定範囲内か(男女とも満50歳以下であること等)確認されます。
契約者(親)が妊娠中の場合の制限: 出産前(140日前)から契約は可能ですが、契約者が妊婦さんの場合、選べる受取総額コースに制限があります。
具体的には受取総額180万円コースまでしか契約できません。
これは妊娠中の契約者に万一のことがあった場合の保険料免除リスクを限定するためと考えられます。出産後であればこの制限はなくなり、上限1500万円コースまで契約可能です。
支払い方法の設定: 保険料の支払いは口座振替かクレジットカード払いを選べます。
毎月払い・半年毎払い・年払いのいずれかを選択し、指定口座からの自動振替またはカード引き落としで支払います。
契約時に初回保険料を払い込み、以降は指定日に自動引き落としされる形です。
年払い・半年払いを選ぶと1回あたりの支出は大きくなりますが、割安な保険料設定となり結果的にお得になります(前述の返戻率向上につながります)。
契約後のフォロー: 契約が成立すると、保険証券と「ご契約のしおり・約款」が送られてきます。
契約内容の確認や各種手続きは、アフラックの契約者専用サイト「よりそうネット」でも管理できます。
また住所変更や受取人変更などがあれば随時手続きを行いましょう。定期的に契約内容のお知らせも郵送されます。
給付金受け取りの流れ:
契約時に定めた学資一時金・学資年金の受取時期が近づくと、アフラックから案内が届く場合があります。
通常は契約者宛に「○○年○月に学資金のお支払いがあります」といった通知や請求書類が送られてきます。
請求手続き: 学資一時金や年金を受け取るには、所定の請求手続きが必要です。
送られてきた請求用紙に必要事項を記入し、契約者(受取人)の本人確認書類や銀行口座情報などと共に提出します。
郵送での手続きが一般的ですが、代理店担当者に依頼して手続きをサポートしてもらうこともできます。
最近では契約者専用サイトや電話で手続き案内を完結できる場合もあります。
給付金の支払い: 請求手続きが完了すると、指定した銀行口座に学資金が振り込まれます。
高校入学時の学資一時金は「子どもが満14歳10か月になった後の最初の2月1日以降」と定められており、概ね中学3年生の終わり頃(高校入学直前)に受け取る形です。
大学入学時からの学資年金は、受取開始年齢(17歳または18歳)に達した後の契約応当日(契約日と同じ日付)に初回が支払われ、以降年に1回、計4年分支払われます。
例えば18歳開始の場合、子どもが18歳の誕生日を迎えた後の契約応当日に第1回年金(基準学資年金額)100万円が支払われ、その1年後・2年後・3年後にそれぞれ50万円ずつ支払われます(合計4回)。
満期後: 大学4年時の学資年金を受け取り終えると契約は満了となります。
その時点で保障も消滅し、以後保険料支払いなどはありません。
満期までに契約者が死亡していて払込免除が発動していた場合でも、満期保険金まで全て予定通り受け取って契約終了となります。
以上が加入から受取までの大まかな流れです。学資保険は長期に渡る契約ですが、適宜案内がありますので難しい手続きは多くありません。
不明点があれば契約時の担当者やアフラックのコールセンターに相談すると良いでしょう。
まとめ
アフラック「夢みるこどもの学資保険」は、高校・大学進学という教育費のかかる節目に合わせて給付金を受け取れる貯蓄型保険です。
親に万一のことがあっても以後の保険料が免除され学資金が受け取れる保障機能を備え、計画的に確実に教育資金を準備できる点で多くの家庭に支持されています。
受取総額や払込期間を柔軟に選べるため、各家庭のライフプランに合わせた設計が可能です。
一方で、返戻率(増やせる率)は他社の学資保険や投資商品と比べて際立って高いわけではなく、払い込み方によっては元本割れとなる可能性もあります。
また長期契約ゆえの途中解約リスクやインフレリスク、設計の自由度の限界など、留意すべき点も存在します。
したがって、本商品を検討する際はメリットとデメリットの両面を理解し、自分たちに向いている商品かどうか見極めることが大切です。
総合的に見れば、「夢みるこどもの学資保険」は堅実に教育資金を貯めたいご家庭にとって心強い選択肢です。
特に「貯蓄が苦手なので強制的に積み立てたい」「万一の保障も欲しい」「信頼できる大手に任せたい」というニーズがある方には適しています。
一方で、「もっと高リターンを狙いたい」「柔軟に資金を使いたい」という方は他の方法(例えばつみたてNISA等での運用や預金など)も含めて検討すると良いでしょう。
教育費は家計に占める割合が大きく、早め早めの準備が肝心です。
学資保険という手段もうまく活用しつつ、児童手当や奨学金制度など公的制度も視野に入れ、計画的に備えていきましょう。
将来、お子さんの夢(「夢みるこども」)を叶える一助として、本記事の情報がお役に立てば幸いです。
参考資料・情報出典: アフラック公式サイト、各種FP解説記事、金融公庫調査データ等(本文中に出典として明記)